こんにちは!現役組み込みソフトウェアエンジニアの竹です。
自動車の制御ソフトウェアを開発していると、必ずと言っていいほど耳にする言葉――それが「AUTOSAR(オートザー)」です。でも、新人エンジニアの方にとっては、「組織の名前?技術?何ができるの?」といまいちピンと来ないかもしれません。
本記事では、AUTOSARとは何か、技術としてどんなものなのか、ClassicとAdaptiveの違い、主要なベンダー情報まで、網羅的にかつわかりやすく解説します。この記事を読めば、明日からの業務でも「AUTOSARって〇〇ですよね」と自信を持って言えるようになります!
AUTOSARとは?

AUTOSARという組織
AUTOSARとは「AUTomotive Open System ARchitecture」の略称で、自動車向けのソフトウェアアーキテクチャの標準化を推進する国際的なコンソーシアム(共同事業体)です。そのコンセプトは次のようになっています。
Cooperate on standards, compete on implementation
“標準化で協調を、実装で競争を”
なぜAUTOSARという組織が必要だったのか?
自動車業界では近年まで、電子制御ユニット(ECU)の数が爆発的に増加しています。エンジン制御、ブレーキ、ステアリング、ADAS(先進運転支援システム)…。これらすべてが個別のECUで制御されており、それぞれがベンダー独自のソフトウェアで開発されていました。
しかしながら、どのECU制御ソフトウェアにも、通信機能やダイアグノーシス(自己診断)、タスク・割り込み管理やメモリ管理といった機能は実装されており、これらを製品ごとに各社がしのぎを削って開発し続けることは自動車業界全体の無駄そのものでした。
AUTOSAR発足とその目的
このような課題を解決するために、BMW、Bosch、Continental、Daimler、Volkswagenといった大手自動車メーカーやメガサプライヤが2003年に立ち上げたのがAUTOSARです。そのためAUTOSARの目指すところは次のようになっています。
- ソフトウェアの再利用性向上
- ECU間のインターフェース共通化
- ソフトウェアとハードウェアの分離
- 標準化による開発効率向上
AUTOSARという技術
AUTOSARは単なる組織ではなく、実際に利用されるソフトウェアアーキテクチャの仕様を提供しています。つまり、AUTOSAR準拠のソフトウェアを作るための「設計図」や「ルールブック」を定めているわけです。
AUTOSARのアーキテクチャの構造
AUTOSARのソフトウェア構造は大きく以下の3層に分かれています:
- Application Layer(アプリケーション層)
→ 車両固有の機能(例:エアバッグ展開、車線維持支援)を実装します。 - RTE(Run-Time Environment)
→ アプリケーション層と下層のインフラ層をつなぐインターフェース層。ミドルウェアのような役割です。 - Basic Software(BSW)
→ OS、通信(CAN/LIN/FlexRay)、メモリ管理、診断など、ハードウェアに近い機能を提供する層です。
この分離構造により、アプリケーションとハードウェアが疎結合になり、ハードウェアを変更してもアプリケーションをそのまま流用できるというメリットが生まれます。
AUTOSAR AdaptiveとClassic
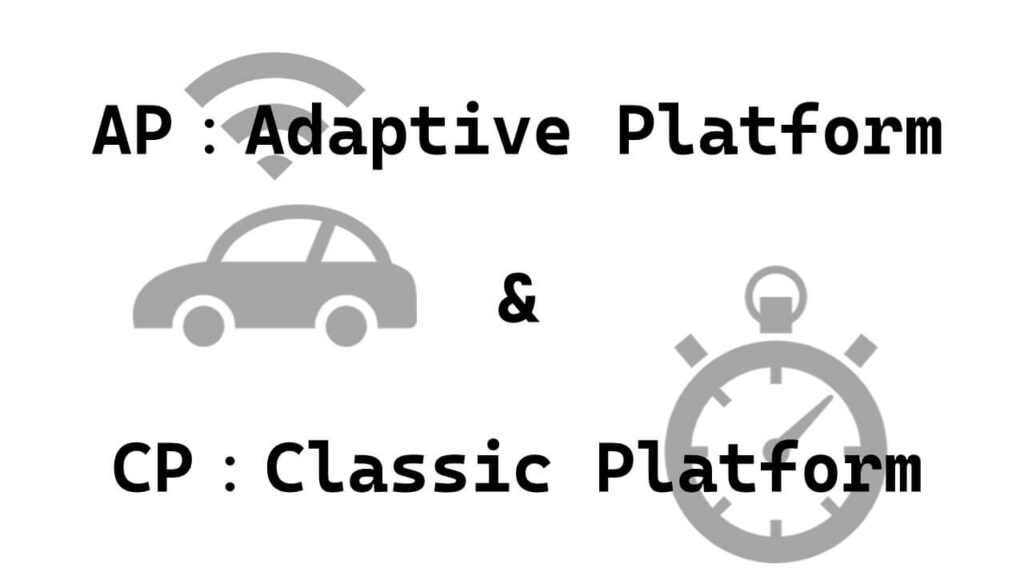
AUTOSARには2つの大きな仕様があります。Classic PlatformとAdaptive Platformです。名前は似ていますが、目的も技術も大きく異なります。
Classic Platform(従来型)
- 対象:制御系ECU(エンジン、ブレーキ、エアバッグなど)
- OS:リアルタイムOS
- 開発言語:C言語
- 特徴:
- 処理性能よりもリアルタイム性と信頼性が重要
- 小規模なマイコンに最適化
- 長年にわたり自動車業界の主流
Adaptive Platform(新型)
- 対象:高機能ECU(自動運転、IVI、OTAなど)
- OS:POSIXベース
- 開発言語:C++、Pythonなども利用可
- 特徴:
- 動的なアプリケーション管理(アプリの起動・停止・アップデートなど)
- 大規模な計算リソースが必要なECU向け
ClassicとAdaptiveの住み分け
- Classic:堅牢でリアルタイム性が重視しており制御に特化
- Adaptive:高性能なECUを見据えた情報処理に特化
将来的には、1台の車に両方のAUTOSAR準拠ECUが共存する「ハイブリッド構成」が一般的になると見られています。
主要なAUTOSARベンダー

AUTOSARはオープンな仕様ですが、実際のソフトウェアスタックやツールは各ベンダーが提供しています。ここでは代表的なベンダーを紹介します。
Vector(ドイツ)
- 世界トップクラスのAUTOSARベンダー
- 特にClassic Platformが広く利用されている
- 開発ツール「DaVinci」シリーズが有名
- 日本市場にも強く、多くのTier1が採用
Elektrobit(EB)
- Continental傘下のソフトウェア企業
- Adaptive Platformでも先進的な実績
- HMIや自動運転系にも強い
- ツールチェーンの整備度が高い
ETAS(ボッシュ系)
- 主にClassic Platform向けのソリューションを提供
- RTA(Real Time Application)シリーズで有名
- BOSCHグループの内部開発でも多数採用
SIEMENS
- Classic AUTOSARスタックを提供
- AUTOSARベンダーMentor GraphicsがSIEMENSに買収され統合
KPIT
- インド系ベンダーで、コストパフォーマンスに優れる
- Classic、Adaptive両対応
- オフショア開発との親和性が高い
まとめ
AUTOSARは単なるバズワードではなく、今や自動車開発には欠かせない基盤技術です。新人エンジニアとしては、以下のポイントを押さえておけばOKです:
- AUTOSARは「自動車ソフトの共通ルールを作る組織」
- 技術としては「アプリとハードを切り離して再利用性を高める仕組み」
- Classicは制御系、Adaptiveは情報系で使われる
- 実際の導入はVectorやEBなどのベンダーが担う
最初はとっつきにくいかもしれませんが、AUTOSARの基本を理解すれば、実務での設計・実装・検証において大きな武器になります。またこちらの記事ではAUTOSARの技術を身に着けるにはどういった学習をすすめればいいかまとめています。
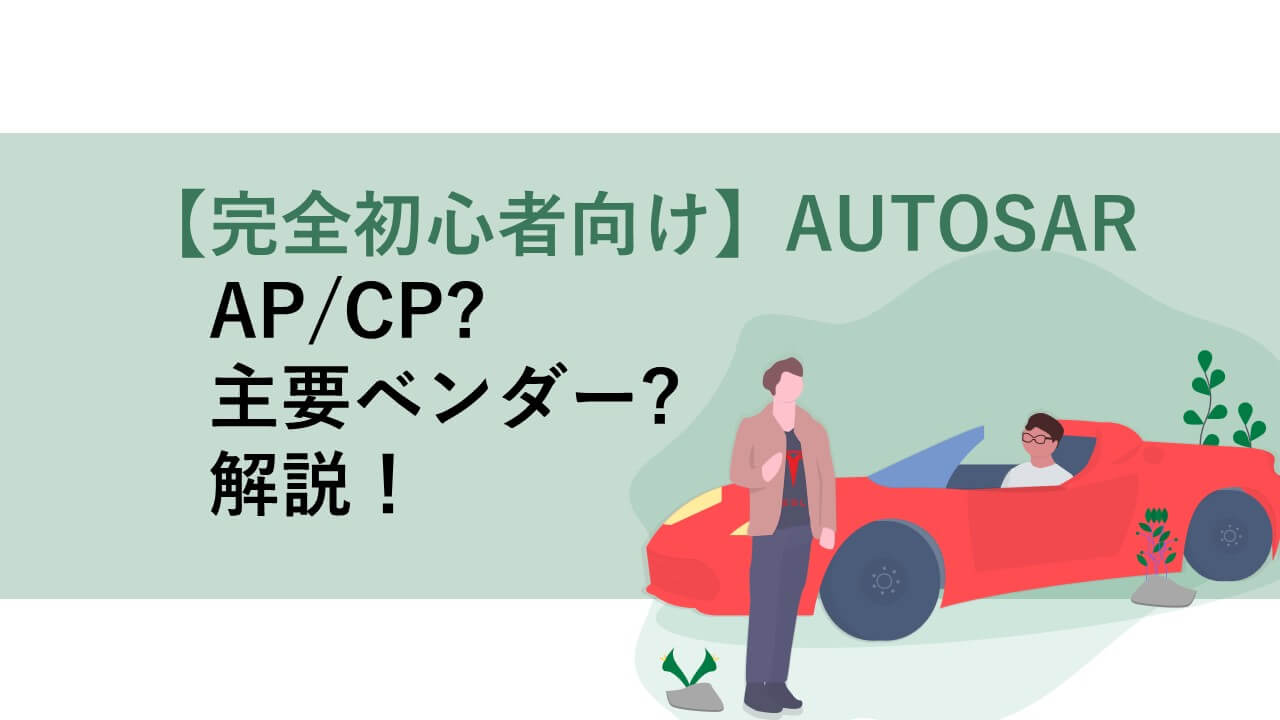


コメント